【漫画チ。】最終回はひどい?ラファウの最期は?地動説についても解説!
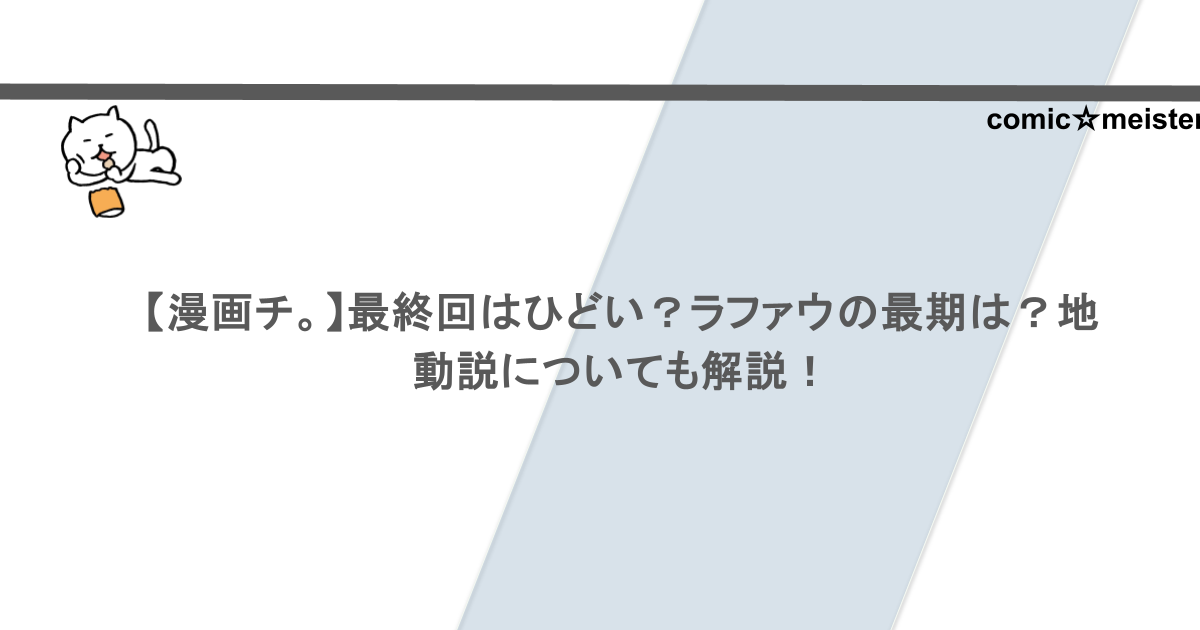
大人気漫画『チ。―地球の運動について―』。哲学と科学、宗教が交錯する物語は高く評価され、数々の賞を受賞しています。
全8巻で完結しましたが、その最終回については賛否両論が起こり、「チ。」の最終回はひどい」という評価まであるほどです。
本記事では、最終回がひどいと言われる理由の考察や、ラファウの最期、そして「地動説」について解説します。
物語の核となる「地動説」とは?
本題に入る前に、物語の核となる「地動説」について簡単におさらいしましょう。
『チ。』の舞台である15世紀ヨーロッパでは、古代ギリシャの天文学者プトレマイオスが体系化した天動説が絶対的な真理とされていました。
夜空を見上げれば星々が動いて見えるため、人々の感覚とも一致しやすく、何より「人間が住む地球こそが宇宙の中心である」という思想がキリスト教の教義と強く結びついていたため、約1400年もの間、常識として受け入れられていました。
| 項目 | 地動説 | 天動説 |
| 中心 | 太陽 | 地球 |
| 地球の動き | 太陽の周りを公転 | 静止している |
| その他の天体の動き | 太陽の周りを公転 | 地球の周りを公転 |
地動説を研究することが許されていなかった
この常識に異を唱え、「地球が動いている」と考える地動説は、神の教えに背く危険な思想とみなされ、研究する者は厳しい弾圧の対象となりました。
特にプトレマイオスが体系化した天動説は、惑星が逆行する現象なども説明できる数学モデルであり、宗教的な理由だけでなく科学的な根拠としても立証しているとされていました。
『チ。』は、そんな時代に命を懸けて「真理」を探求し、知のバトンを繋いでいこうとする人々の物語となっています。
【漫画チ。】最終回がひどいといわれる理由を調査
数多くある漫画の中には終末のワルキューレ ひどいといった声もあります。
今回テーマとしている漫画「チ。」も、なぜ多くの読者から最終回がひどいという声が上がったのでしょうか。その理由として挙げられる代表的な4つのポイントを元に詳しく見ていきましょう。
①内容が複雑でフィクションから現実世界へ移動
『チ。』の最終回がひどいと批判される理由は何だったかを考えてみましょう。
ジャンルは変わりますが、セトウツミの映画ひどいと言われた内容とは逆で、「チ。」は複雑すぎる内容にあったのではないかと思います。
最終章では、これまで登場しなかった実在の天文学者「アルベルト・ブルゼフスキ」が主人公となり、物語が展開します。3章までの登場人物たちのその後が描かれることを期待していた読者にとっては、「一体何が起こっているんだ?」と困惑する展開でした。
15世紀ヨーロッパの歴史や哲学が複雑に絡み合う中で、この唐突な変更などが、物語をさらに難しくしてしまったのではないでしょうか。
②ラファウの再登場に困惑
最終回で読者を驚かせたのは、物語の序盤で自ら命を絶ったはずのラファウが、青年の姿で再登場したシーンです。死んだはずのキャラクターが何の説明もなく現れたことで、読者の間では、
- 「パラレルワールドなのか?」
- 「実は生きていたという世界線?」
- 「これまでの物語は夢だった?」
など、様々な憶測が飛び交いました。
この青年ラファウは、第1章の知的好奇心旺盛な少年とは異なり、目的のためなら殺人も厭わない狂気的な人物として描かれています。その人格の変貌も相まって、彼の存在が何を意味するのかは描かれていません。
このこの曖昧さが、作品の面白さと同時に、混乱の元にもなったのではないでしょうか。
③衝撃的な処刑や拷問のシーン
最終回に限りませんが、『チ。』では異端者への処刑や拷問が生々しく描かれています。
この描写には15世紀ヨーロッパの残酷な現実を伝え、真理の探求がいかに命がけであったかを示す意図があったとも考えられます。歴史の光だけでなく、その暗い側面にも目を向ける重要性を示したかったのかもしれません。
しかし、インパクトの強い描写が物語のテーマ以上に読者に残ってしまったため「ひどい」という印象になってしまったのかもしれません。
④開かれた結末への批判
『チ。』の結末は、明確な答えを示さず、多くの謎を読者の解釈に委ねる「開かれた結末(オープンエンディング)」です。
特に、地動説を歴史的に確立したコペルニクスの物語が一切描かれずに終わったことに対し、「地動説の物語なのに、そこを描かないのは不完全燃焼だ」という不満の声が多く上がりました。
しかし一方で、「読者が自ら結末を考え、物語のテーマと深く向き合う余地を残した素晴らしい終わり方だ」と評価する声もあります。
「疑問を持ち、考え続けることの重要性」をテーマとした本作にとって、読者自身に思考を促すこの結末は、ある意味で最もふさわしい締めくくりだったのかもしれません。
ラファウの最期と最終回の謎を徹底考察
賛否両論を呼んだ最終回ですが、そこには作者の深い意図が隠されていると考えます。
ここでは、物語の鍵となるラファウの行動や、最終回の哲学的な背景について考察します。
他にも、感想なども交えた考察をしている方もいらっしゃったので、ご紹介しておきますね!
出典元:【チ。 ―地球の運動について―】最終回・第25話解説・感想。アルベルト=人間の真理がわかる完結回。アニメ補足も完璧すぎて号泣した最高の結末【ED変更で泣いた】【伝書鳩】【司祭の正体】【?】
ラファウはなぜ自ら死を選んだのか?
第1章の主人公ラファウは、なぜ改心を拒み、自ら毒を飲んで死を選んだのでしょうか。その答えは、ノヴァクとの最期の対話に隠されています。
ソクラテス曰く「誰も死を味わってないのに誰もが最大の悪であるかのように決めつける。」(引用:第1集)
ラファウは死の直前、古代ギリシャの哲学者ソクラテスの言葉を引用します。ソクラテスは、自らの思想を曲げることを拒み、毒杯を仰いで死刑を受け入れました。ラファウもまた、地動説という「知」への感動と好奇心に殉じることを選んだのではないでしょうか。
青年ラファウの再登場が意味するものとは?
最終回で再登場した青年ラファウは何者だったのでしょうか。
少し見方を変えると「登場人物は哲学的なテーマを語るための記号である」という見方ができます。
物語の序盤で死んだはずのラファウをあえて再登場させることで、作者は「この物語の登場人物は、歴史上の個人というよりも、ある思想や概念を象徴する存在」ということを強調したかったのではと考えられます。
つまり、少年ラファウも青年ラファウも、「知のためなら全てを犠牲にする狂気的な探求心」という概念を象徴し、時代や世界線を超えて存在するテーマであるとも取れます。
なぜアルベルトだけが生き残り、未来へ繋げたのか?
歴代の主人公たちが次々と命を落とす中、なぜ最終章の主人公アルベルトだけが生き残り、コペルニクスへと知のバトンを繋ぐことができたのでしょうか。
アルベルトは他の主人公とは違った?
アルベルトは、他の主人公たちと異なり、教会権威を一方的に否定しなかった点にあります。
アルベルトは、教会の司祭との対話に耳を傾け、自分なりの答えを見出そうとしました。
「この世の美しさ」を知るために、真理を隠そうとする者も、過激に排除しようとする者も、どちらも間違っていると批判しています。
他の主人公たちが純粋な「知」や「血」に殉じたのに対し、アルベルトはバランスを取りながら現実世界で知を実践し、次世代へと繋ぐ役割を果たしたのではないでしょうか。
まとめ
『チ。』の最終回は、確かに複雑で難解な部分が多く、「チ。」の最終回がひどいと感じる読者がいるのも無理はありません。しかし、その展開の裏には、物語全体を貫くテーマが隠されていたのではないかと思います。
読者に「なぜ?」と考えさせる開かれた結末こそが、「知」を描き続けた『チ。』という作品に最もふさわしい終わり方だったと言えるのかもしれません。